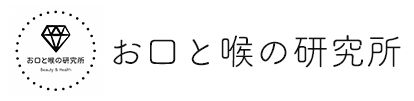オモチのキモチ
年末年始の風物詩「お餅」…実は危険?
寒い季節になると、年末年始の風物詩として「お餅」が欠かせません。雑煮や焼き餅、おしるこなど、家族で温かい食卓を囲むのにぴったりの食材ですね。しかし、この「お餅」、実は日本での窒息事故の原因として上位にランクインする危険な食べ物でもあるのです。
なぜお餅で窒息するのか?
お餅は、独特の「粘り」と「弾力」が魅力ですが、この性質こそが窒息のリスクを高めています。温かく柔らかいときには口の中で伸びるような感覚が楽しめる一方で、冷えると固くなり、噛む力がないと飲み込みにくくなります。特に、年齢を重ねて咀嚼力や嚥下力が弱まっている高齢者にとっては、お餅がのどに詰まりやすく、事故のリスクが高まるのです。
お餅が原因の窒息事故はどれほど多いの?
実は、お正月には毎年、お餅による窒息事故が報道されます。中でも多いのが高齢者ですが、子どもも油断は禁物です。過去の統計によると、お正月シーズンには特に多くの救急搬送が記録されており、日本の伝統食であるお餅の食べ方には細心の注意が必要です。
窒息を防ぐための「お餅の食べ方」
1. 小さく切る:まず、一口サイズに切ってから食べることが重要です。大きなお餅をそのまま口に入れると、詰まりやすくなります。
2. よく噛んでゆっくり食べる:もちをゆっくりと噛むことで唾液がよく混ざり、飲み込みやすくなります。「しっかり噛む」が何よりの予防策です。
3. 飲み物を近くに用意する:お餅は粘りが強いため、万が一詰まったときに飲み物で流しやすくするため、温かいお茶などを準備しておくと良いでしょう。
万が一窒息してしまった場合の対処法
窒息は一刻を争う緊急事態です。救急車を呼びつつ、応急手当を試すのも手です。
背中を強く叩いて詰まったものを吐き出させる方法や、腹部を圧迫する方法が知られていますが、窒息予防のためにも、ゆっくり、少しずつ食べる習慣が一番の対策です。
お餅は日本の伝統食であり、温かい家庭の食卓を彩る食材ですが、安全に楽しむためには、食べ方に気をつけることが大切です。
年末年始、家族で過ごす楽しいひとときに、食の安全も意識してみましょう。